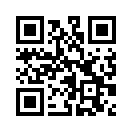2008年10月14日
月待ちのしつらい
 風子と星樹は秋の深まった二宮町一色地区の里山を散策するのが好きです。
風子と星樹は秋の深まった二宮町一色地区の里山を散策するのが好きです。この地区を流れる葛川沿いの桜並木散策道で10月18日(土)に葛川秋の大収穫祭が開催されるので、今年も遊びに行こうと思っています。
風子と星樹が日頃から興味を抱いている地域ブランドづくり「湘南♡風と星物語」も今年は出店するそうです。地域ブランドづくり「湘南♡風と星物語」は歳時記を作り、季節ごとにテーマを決めてラディアン日曜朝市等のイベントに出店していますが、秋は「月待ち」を題材にして、葛川秋の大収穫祭に出店するそうです。
出店内容です。「京の味圓山」の出店ブースに便乗しているそうですので、ぜひ立ち寄ってみようと思います。


★秋の彩り弁当〈京の味 圓山〉〈自然農法ぽんぽこファーム〉〈有機農園つ・む・ぎ〉
月待ちは多くの人が集まって興じたということから、みんなで楽しめる秋の味覚満載で彩り豊かなお弁当を作ってみました。
地元二宮の原木生しいたけをふんだんに入れた「きのこご飯」に地場の無農薬野菜を彩りよく使ったお弁当です。京風煮物、十三夜が豆名月といわれるようにこの時期に美味しい枝豆や甘味にさつまいもの茶巾しぼりが入っています。
★子じゃが串あげ〈有機農園つ・む・ぎ〉
十三夜には収穫祭という意味合いもあって子ども達がお供え物の団子を竹竿にさして盗んでも大人に怒られず、それを楽しみしていたという地方もあったようです。
今ハロウィンになぞらえたイベントが様々なところで開催されていますが、日本のこんな風習をイベントになぞらえても楽しいのではないでしょうか。
こんな光景を想像して、ちいさなじゃがいもを団子に見立て揚げてみました。
★八海山金銀ひょうたんボトル〈Bon蔵ウチヤマ〉
十三夜には平安時代に貴族達が集まって、月を見て詩歌を読んで興じたと言われています。そんな時お酒は重要な役割を持っていたと思います。
収穫を祝い、銘酒八海山の純米酒と吟醸酒を金銀のひょうたんにいれて供えてみました。このお酒を飲んで、秋の夜長に文をしたためてみるのも一興かもしれません。
★神(かん)丹(に)穂(ほ)のリース・実りのリース〈日和〉
「神丹穂」は、黒米の一種の装飾用の稲穂です。
秋の恵みを祝い、美しい紅色の色合いの稲穂「神丹穂」のリースを揃えました。
また、秋の恵みを感じる様々な実をリースにした実りのリースも揃えてみました。
地域ブランドづくり「湘南♡風と星物語」は、二宮町を地域探険して発見した伝承や魅力を生かしながら、単なる名産品づくり、観光化ではない、作り手の想いやその地域づくりまでがわかり、人々に共感を与える地域ブランドづくりをしたいと考え、農業者、様々な業種の商業者、地域活動者、専門家が集まり、検討や試作を重ねています。
名前に「星」を入れたのは、二宮町に星にまつわる伝承や行事が様々残り、季節感や旬、希望や願いを込めたからだそうです。
今回は、星(月)が収穫を祝う行事と密接に関係していることから、葛川秋の大収穫祭に「月待ちのしつらい」をテーマに参加するそうです。「京の味圓山」の出店ブースに便乗し、昔から息づく人々の自然への感謝や想いを「物」に託して暮らしの中に取り入れる「しつらい」として展示販売するそうです。
昔から長く伝えてきた風習や行事には、先人が大切にしてきた想いが込められています。私たち現代人が、忙しさや効率性の中で失ってしまったものを見直し、アレンジして提供することで、私たちの暮らしに潤いや安らぎ、楽しみが与えられるのではないかと考えているそうです。
 月待ちのいわれ
月待ちのいわれ
「お月見」は、満月などを楽しむことで、「十五夜(旧暦8月15日)」と十三夜(旧暦9月13日)に行われます。
十五夜の月を鑑賞する習慣は中国から伝わりましたが、十三夜は平安時代に貴族達が集まって、月を見て詩歌を読んだのが始まりだとも言われ、日本独特の風習だと言われています。
「月待ち」は、ある特定の形の月が昇るのを待って、多くの人が集まり、供え物をしたり拝んだりする行事を言うそうです。
日本では古来より十三夜(旧暦9月13日)の夜は晴れることが多いようで、特に美しい月として重んじられていたそうです。今年は10月11日がこの日に当たります。
名前に「星」を入れたのは、二宮町に星にまつわる伝承や行事が様々残り、季節感や旬、希望や願いを込めたからだそうです。
今回は、星(月)が収穫を祝う行事と密接に関係していることから、葛川秋の大収穫祭に「月待ちのしつらい」をテーマに参加するそうです。「京の味圓山」の出店ブースに便乗し、昔から息づく人々の自然への感謝や想いを「物」に託して暮らしの中に取り入れる「しつらい」として展示販売するそうです。
昔から長く伝えてきた風習や行事には、先人が大切にしてきた想いが込められています。私たち現代人が、忙しさや効率性の中で失ってしまったものを見直し、アレンジして提供することで、私たちの暮らしに潤いや安らぎ、楽しみが与えられるのではないかと考えているそうです。
 月待ちのいわれ
月待ちのいわれ「お月見」は、満月などを楽しむことで、「十五夜(旧暦8月15日)」と十三夜(旧暦9月13日)に行われます。
十五夜の月を鑑賞する習慣は中国から伝わりましたが、十三夜は平安時代に貴族達が集まって、月を見て詩歌を読んだのが始まりだとも言われ、日本独特の風習だと言われています。
「月待ち」は、ある特定の形の月が昇るのを待って、多くの人が集まり、供え物をしたり拝んだりする行事を言うそうです。
日本では古来より十三夜(旧暦9月13日)の夜は晴れることが多いようで、特に美しい月として重んじられていたそうです。今年は10月11日がこの日に当たります。
Posted by tomo at 22:00│Comments(0)
│名物思案中?!
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。